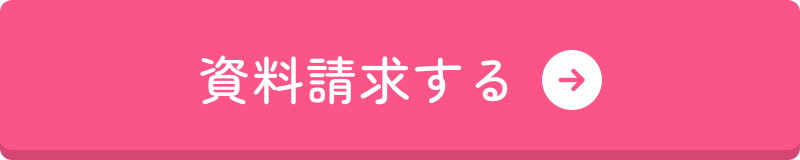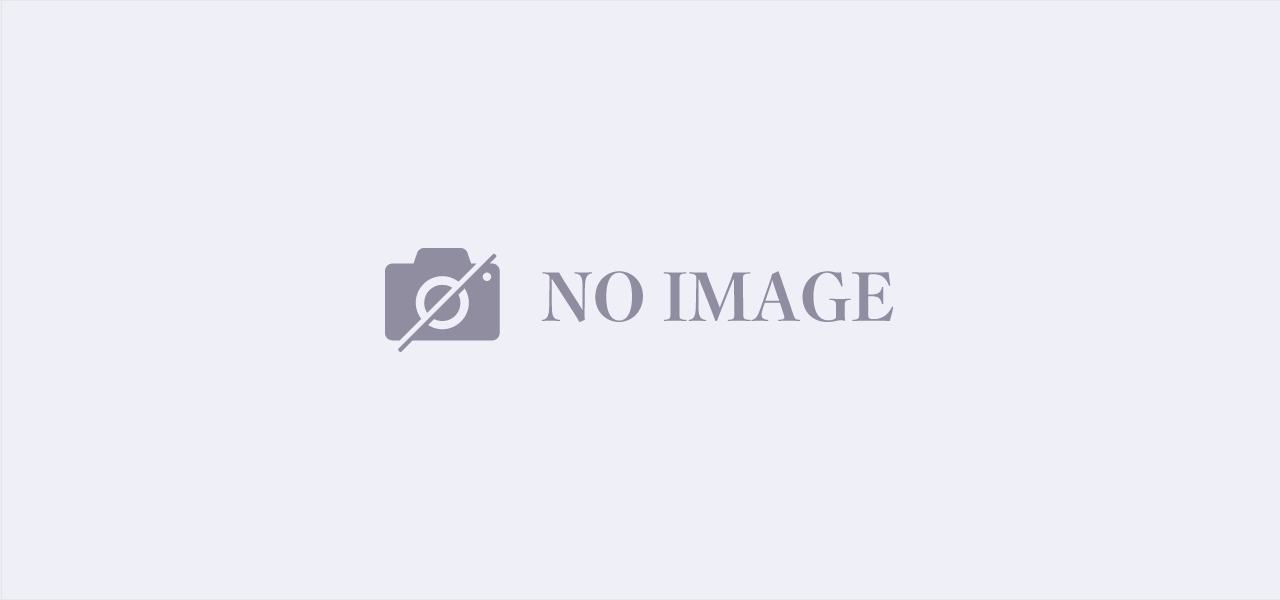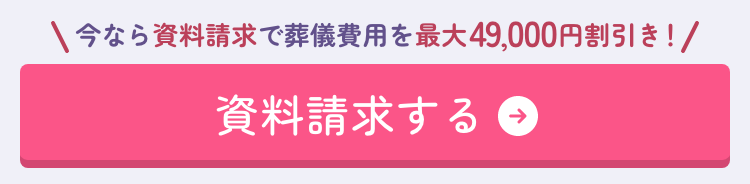家族葬
特集
家族葬特集
記事公開日:2025.11.07/最終更新日:2026.01.09
記事公開日:2025.11.07
最終更新日:2026.01.09
家族葬の費用内訳を徹底解説|平均相場と節約のポイント
近年、故人を静かに見送るスタイルとして「家族葬」を選ぶ方が増えています。規模が小さいため費用を抑えやすく、遺族の精神的な負担を軽減できる点が大きな理由です。ただし、費用の内訳や選ぶプランによって総額は変わるため、正確な情報を理解しておくことが大切です。
本記事では、家族葬の費用相場から内訳、そして節約の工夫までを詳しく解説していきます。
目次
家族葬の費用相場

家族葬の費用は、全国調査によると平均で約105.7万円とされ、一般葬の平均161.3万円に比べて抑えられる傾向があります。
内訳をみると、まず基盤となるのが基本料金(約75.7万円)で、式場の使用料や祭壇、棺、火葬料、遺影、搬送費などが含まれます。これは葬儀の規模にかかわらず必要となるため、家族葬でも一定の金額がかかるのが特徴です。(参考:【第6回】お葬式に関する全国調査(2024年) アフターコロナで葬儀の規模は拡大、関東地方の冬季に火葬待ちの傾向あり)
一方で変動するのが参列者数に応じた費用です。具体的には飲食費が平均約20.7万円、返礼品費が約22万円となり、人数が少ない家族葬ではここを大きく削減できるのが特徴できます。実際、規模を小さくすれば60万円台で行える場合もあれば、祭壇や料理を充実させれば100万円を超えることもあるでしょう。
つまり家族葬は「必ず安い葬儀」ではなく、選ぶ内容によって総額が大きく変わります。無理のない範囲でどこに重点を置くかを決めることが、納得できる葬儀につながるでしょう。
家族葬の費用内訳

家族葬は、一般葬に比べて費用を抑えられるといわれますが、その内訳を正しく理解することが大切です。
大きく分けると、式場や祭壇にかかる「基本料金」、必ず発生する「火葬料」、そして参列者の人数によって変動する「返礼品・飲食費用」の三つがあります。それぞれの金額感や特徴を知っておくことで、無理のない予算計画を立てることができるでしょう。
以下では項目ごとに詳しく見ていきます。
式場使用料
式場使用料は、葬儀一式の基本料金に含まれることが多く、全国調査ではこの基本部分の平均が約75.7万円とされています。(参考:【第6回】お葬式に関する全国調査(2024年) アフターコロナで葬儀の規模は拡大、関東地方の冬季に火葬待ちの傾向あり)
その中には式場の利用料のほか、棺、遺影、霊柩車や搬送なども含まれますが、とりわけ式場の選び方が費用に影響を及ぼします。都市部の会場や交通アクセスの良い斎場では料金が高めに設定されやすく、逆に公営の式場や自宅葬を選べば抑えることも可能です。
設備や立地条件だけでなく、家族の希望や参列人数に合った会場を選ぶことが、費用と満足度の両立につながります。
祭壇・装飾費用
祭壇や装飾は、葬儀の雰囲気を大きく左右する要素です。調査によれば、祭壇や会場装飾にかかる費用は基本料金の中でも大きな割合を占め、20万円から40万円程度が目安とされています。(参考:【第6回】お葬式に関する全国調査(2024年) アフターコロナで葬儀の規模は拡大、関東地方の冬季に火葬待ちの傾向あり)
最近では生花を主体にした花祭壇が主流になっており、シンプルであれば比較的安価に抑えられますが、色鮮やかで大規模な装飾を希望すれば費用が大きく上がります。故人の好みや家族の意向を反映させることは大切ですが、豪華にしすぎると予算を圧迫しかねません。
費用を考えながら、故人らしさを表現できる適度な装飾を選ぶことが望ましいでしょう。
火葬料
火葬にかかる費用は、地域や火葬場の運営形態によって幅があります。公営の火葬場を利用すれば数千円から数万円程度で済むケースが多い一方、民営施設の場合は数万円から10万円前後になることもあります。
家族葬の総額平均である105.7万円のうち、火葬料は必ず含まれる基本的な支出であり、規模の大小に関わらず避けられない費用です。
特に都市部では火葬待ちの影響もあり、希望通りの日程が取りづらいこともあるため、料金だけでなくスケジュール面も考慮に入れておくことが重要です。
返礼品・飲食費用
返礼品や飲食にかかる費用は、参列者の数に比例して変動する大きな要素です。調査データでは返礼品が平均22万円前後、飲食が約20.7万円とされており、両者を合わせると40万円を超えることになります。(参考:【第6回】お葬式に関する全国調査(2024年) アフターコロナで葬儀の規模は拡大、関東地方の冬季に火葬待ちの傾向あり)
ただし、家族葬は参列人数が少ないため、この部分を大きく削減できるのが大きなメリットです。例えば、返礼品を必要最小限にしたり、通夜振る舞いや精進落としを親族中心に限定したりすることで、総額を抑えつつも心のこもった対応が可能です。
人数や規模の調整によって柔軟に対応できる点は、家族葬ならではの強みといえるでしょう。
一般葬との費用比較

家族葬と一般葬の最大の違いは参列者数にあり、それが費用差にも直結します。全国調査では、一般葬の平均費用は約161.3万円、家族葬は約105.7万円とされ、約50万円以上の差が出ています。(参考:【第6回】お葬式に関する全国調査(2024年) アフターコロナで葬儀の規模は拡大、関東地方の冬季に火葬待ちの傾向あり)
両者で大きく異なるのは飲食費や返礼品費といった変動費です。一般葬では参列者が多いため飲食に30万円以上、返礼品に40万円近くかかる場合があり、合計で70万円を超えることも珍しくありません。
一方、家族葬は参列者が限られるため、これらは40万円前後に収まる傾向があります。ただし式場使用料や祭壇費用、火葬料などの基本料金は規模に関係なく必要となるため、両者の差は大きくありません。
つまり家族葬は、人数に比例して増える部分を抑えることで、総額を軽減できる葬儀形式だといえるでしょう。
家族葬の費用を抑える工夫

家族葬の費用は工夫次第で大きく変わります。特に効果があるのは、どのプランを選ぶか、そして参列者をどの範囲にするかの二点です。ここではそれぞれの工夫について具体的に解説します。
プラン選び
葬儀の費用を抑えるためには、プランの内容を慎重に選ぶことが欠かせません。標準的な家族葬は通夜と告別式を行いますが、通夜を省略して一日で終える「一日葬」を選ぶことで、会場費や人件費を減らせます。
さらに、火葬だけを行う「直葬(火葬式)」では、宗教儀式や会場装飾を省くため、全体の支出を大きく抑えられます。こうした形式は費用削減に直結する一方、故人とのお別れの時間が短くなるため、家族の希望と照らし合わせて選ぶことが大切です。
また、公営の斎場を利用すれば会場費用を低くできる場合もあり、地域によっては数万円単位で差が出ることもあります。複数の葬儀社や施設を比較し、家族の意向と予算の両面から納得できるプランを見つけることが、無理のない葬儀につながるでしょう。
会葬者数の調整
参列者数の調整は、家族葬の費用を抑える上で最も効果的な方法のひとつです。飲食費や返礼品費は人数に比例して増えるため、参列者を親族や特に親しい友人に絞るだけで、総額を数十万円単位で削減できる可能性があります。
例えば、30人規模と10人規模の家族葬では、返礼品や料理の準備費用に大きな差が出るのです。ただし、人数を減らす際には関係者の気持ちに配慮する必要があります。
呼ばなかった人には事前に状況を説明したり、後日改めてご挨拶をするなど、丁寧な対応を心掛けることが望ましいでしょう。無理のない範囲で人数を絞ることで、経済的負担を軽減すると同時に、落ち着いた雰囲気の中でゆっくりと故人を偲ぶ時間を持てます。このような調整は、費用面だけでなく心の満足度を高める工夫にもなるのです。
「はないろ」ならわかりやすい料金プランで安心

葬儀の費用はわかりにくく、思った以上に負担が大きくなるのではと心配される方も少なくありません。家族葬専用式場「はないろ」では、その不安を解消するために明朗な料金設定を導入し、誰でも理解しやすいプランを用意しています。
火葬式・一日葬・家族葬・家族葬プラスといった複数のプランがあり、費用はセット料金で提示されるため、追加費用の不透明さに悩まされることがありません。また、事前に備えることで割引を受けられる「生前そなえ割」などの制度も整っており、将来の負担を軽くしたい方にも適しています。
さらに、24時間365日専門スタッフが対応しているため、急な相談にもすぐ応じてもらえる安心感があります。厚生労働省認定の葬祭ディレクター資格を持つスタッフも多数在籍し、葬儀の進行だけでなく、法要や供養のサポートまで幅広く支えてくれるのも大きな特徴です。
背伸びをせず、それでいて故人を丁寧に見送れるよう寄り添ってくれる「はないろ」は、費用面でも心の面でも頼れる存在といえるでしょう。
まとめ
家族葬の費用は、式場や祭壇などの基本費用に加え、参列者数によって変動する飲食や返礼品が大きな割合を占めます。平均は100万円前後といわれていますが、プラン選びや人数の調整次第で総額は大きく変わります。そのため、あらかじめ費用の内訳を把握し、自分たちに合った形を選ぶことが大切です。
家族葬専門式場「はないろ」では、火葬式から家族葬まで明朗な料金プランを用意し、追加費用の心配を少なくしています。さらに24時間365日、専門スタッフが相談に応じてくれるため、急な備えにも安心です。費用を抑えつつ心のこもったお別れを望む方は、まず「はないろ」へお気軽にお問い合わせください。