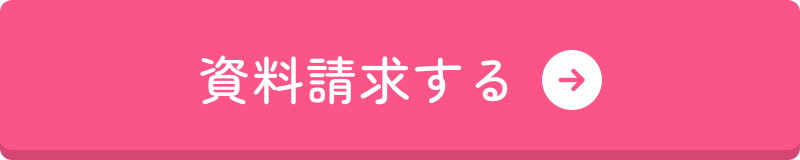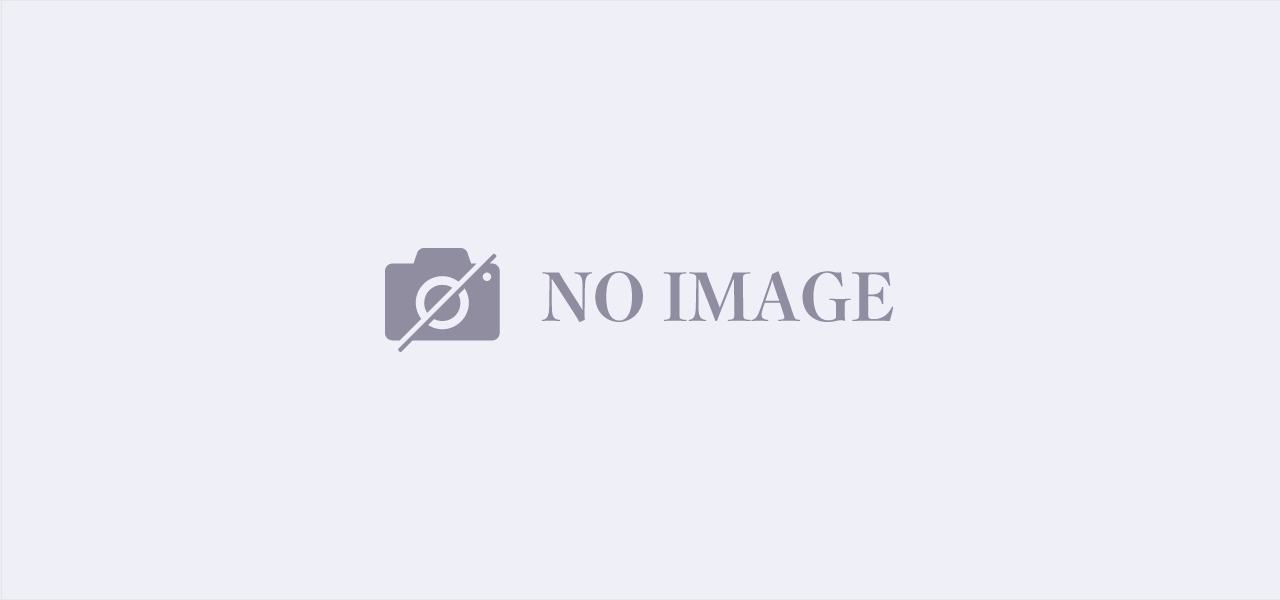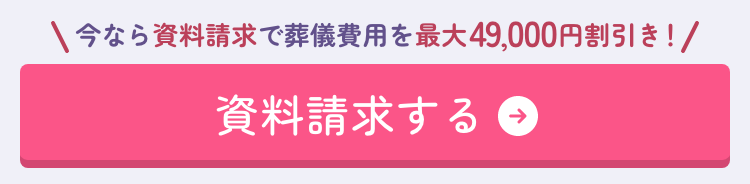家族葬
特集
家族葬特集
記事公開日:2025.11.10/最終更新日:2026.01.09
記事公開日:2025.11.10
最終更新日:2026.01.09
家族葬の流れをわかりやすく解説|準備から葬儀後まで
近年、多くのご家庭で選ばれるようになったのが「家族葬」です。参列者を近しい親族やごく限られた友人に絞ることで、故人との時間を落ち着いた雰囲気の中で過ごせるのが特徴です。
一方で、香典の扱いや参列できなかった人への配慮など、注意すべき点もあります。この記事では、家族葬の準備から葬儀後の流れまでをわかりやすく解説し、初めての方でも安心できるよう丁寧にご案内します。
目次
家族葬の全体の流れ(準備〜葬儀後)

家族葬は、規模を抑えて親しい人たちだけで故人を見送る形式ですが、その進行の基本は一般的な葬儀と大きく変わりません。
ご臨終後には葬儀社への連絡を行い、遺体を安置して式場を決め、打ち合わせやプランの決定といった準備を整えます。続いて通夜が営まれ、挨拶や読経、焼香を通じて参列者が故人を偲びます。
翌日の告別式では再び読経があり、弔辞や焼香のあと出棺へと進み、火葬が行われ、収骨の儀を経て一連の葬送が終了です。葬儀を終えた後も、精進落としや法要、香典返し、役所での諸手続きといった事務的な対応が続きます。
また、初七日法要を告別式と同日に繰り上げて行う例や、式後すぐに会食を行う形も増えており、近年の家族葬は柔軟性が高い点も特徴です。このように準備から葬儀後までを一連の流れとして理解しておくことが、落ち着いた見送りにつながります。
葬儀前の準備

家族葬を落ち着いて進めるためには、事前の準備が重要です。特に「式場選び」「葬儀社との打ち合わせ」「プランの決定」は、当日の流れを大きく左右する基本的なステップになります。ここでは、それぞれの準備について具体的に解説します。
式場選び
家族葬の式場を選ぶ際に大切なのは、参列者の人数や交通の便、そして遺族の意向に合った環境かどうかです。少人数の場合は、小規模の専用ホールや寺院の一室、自宅近くの会館なども候補になります。
例えば、公共交通機関からアクセスしやすい場所を選べば、高齢の参列者にとっても安心です。また、宿泊施設の有無や駐車場の広さといった細かい条件も確認しておくことで、当日の不安を軽減できます。こうした基準を踏まえて選ぶことで、参列者にとっても故人にとっても納得のいく式場を決定できます。
打ち合わせ
式場が決まったら、葬儀社との打ち合わせが始まります。この段階で日程や進行内容をすり合わせ、宗教形式や参列規模を明確にします。
打ち合わせでは、喪主の役割分担、式の進め方、参列者への連絡方法、祭壇や会場装飾の希望など、細かい部分まで話し合うことが肝心です。ここで十分に相談しておけば、当日の進行がスムーズになり、遺族が落ち着いて式に臨めます。特に費用面の確認を怠らないことで、後のトラブルを防ぐことが可能です。
プラン決定
最後に、葬儀の具体的なプランを決定します。基本プランに加えて、湯灌や納棺の儀といったオプション、祭壇や花のデザイン、会食の有無などを選択しましょう。
このとき、費用と内容を比較しながら、故人らしさを表現できるかどうかを基準に検討するのがおすすめです。最終的にプランを確定することで、準備が整い、遺族は式に集中できる環境をつくれます。
通夜の流れ

家族葬における通夜は、故人と過ごす最後の夜を静かに偲ぶ大切な時間です。進行は大きく「挨拶」「読経」「焼香」の3つの流れに分かれています。
小規模で行う場合でも基本の順序は一般葬とほぼ同じですが、人数が限られる分、一人ひとりがより深く故人と向き合えるのが特徴です。ここでは、それぞれの場面ごとに具体的な内容と意味を整理していきます。
挨拶
通夜の開式にあたり、まず司会者や喪主からの挨拶が行われます。この場面では、参列してくださった方々への感謝の言葉が伝えられると同時に、通夜が始まることが正式に告げられます。
家族葬の場合、参列者の多くは親族や親しい友人に限られるため、形式的な決まり文句よりも、心情を込めた言葉が選ばれる傾向が高いです。
例えば「本日はご多忙の中、父のためにお集まりいただきありがとうございます」といった素直な表現が場を和ませ、参列者に温かさを感じさせます。この挨拶が終わることで会場全体が落ち着き、読経へと自然に移行できる雰囲気が整えられるのです。
読経
挨拶に続いて行われるのが僧侶による読経です。これは故人の冥福を祈る中心的な儀式であり、通夜全体の核ともいえます。宗派によって唱えられるお経の内容や長さは異なりますが、一般的には30分から1時間程度かかります。
参列者は手を合わせながら静かに耳を傾け、心を整える時間を持ちます。特に家族葬の場では人数が限られるため、形式的に流れるのではなく、一人ひとりがじっくりと故人を思い出しやすい環境になります。
また、近年では僧侶による説法を短く加えるケースもあり、参列者が仏教的な意味合いを理解しやすくなる工夫も見られるのが特徴です。こうした読経の時間は、故人を送るだけでなく、遺族にとって心を整理する大切な機会にもなっています。
焼香
読経が終わると、焼香が行われます。焼香は、香を焚いてその煙で心身を清め、故人に敬意を表す儀式です。
最初に僧侶が焼香し、その後に喪主、遺族、親族、一般参列者の順に続きます。会場によっては立ったまま行う「立礼焼香」、正座で行う「座礼焼香」、あるいは香炉を参列者に回していく「回し焼香」など、さまざまな形式が用いられます。
基本的な作法は、焼香台の前で一礼し、香を右手でつまんで額に軽くあててから香炉にくべ、静かに合掌して席へ戻るという流れです。家族葬では参列者が少ないため、一人ひとりの所作がより丁寧に行われる傾向があり、故人に対する想いをしっかりと込められます。焼香は短い時間であっても、参加者全員の気持ちが一つになる象徴的な場面となります。
告別式の流れ

告別式は、通夜に続いて行われる葬送の中心的な儀式です。宗教的なお祈りと社会的なお別れが結びついた場であり、一般的には「読経」「弔辞」「焼香」「出棺」という順序で進みます。
家族葬では参列者が限られているため、全体に落ち着いた雰囲気が保たれ、一人ひとりが故人に心を寄せる時間を持てるのが大きな特徴です。
読経
告別式の冒頭で行われる読経は、僧侶によって故人の冥福を祈る大切な儀式です。宗派によって経典や唱える内容は異なりますが、概ね30分から1時間程度かけて厳粛に進められます。
通夜よりも儀式としての意味合いが強く、式全体の空気を引き締める役割を担います。参列者は静かに手を合わせ、読経に耳を傾けながら心を整えます。小規模な家族葬では、場の静けさの中で一人ひとりが故人を近くに感じられるのが特徴で、形式に流されるのではなく、深い祈りの時間を共有できます。
弔辞
読経が終わると、故人と縁の深い方から弔辞が読まれることがあります。弔辞には生前の思い出や人柄、故人との関わりが語られ、式の中でも特に感情がこもる時間です。
一般的には数分程度でまとめられますが、内容は形式にとらわれず、心からの言葉であることが重視されます。家族葬の場合、弔辞を依頼されるのはごく親しい人であることが多く、参列者も少人数であるため、より親密で温かい雰囲気の中で読まれるのが特徴です。
時には弔電が披露されることもあり、離れた場所から寄せられた想いが会場を包むこともあります。
焼香
弔辞に続いて行われるのが焼香です。僧侶を先頭に、喪主、遺族、親族、一般参列者の順で進みます。焼香は香を額に軽くあて、香炉にくべて合掌するのが一般的な作法で、立礼・座礼・回し焼香など、会場の状況に応じた形で行われます。
家族葬では参列者の人数が限られているため、一人ひとりがゆっくりと落ち着いて焼香できるのが特徴です。短い所作であっても、故人への敬意と感謝の気持ちを表す大切な時間であり、参列者の心をひとつにする場面といえます。
出棺
告別式の最後を締めくくるのが出棺です。参列者は故人が納められた棺に手を合わせ、別れの言葉をかけながら見送ります。
棺は霊柩車に移され、火葬場へと向かいますが、このとき喪主や遺族が感謝を述べる挨拶を行うことが多く、参列者は静かに見守りながら最後の別れを告げます。家族葬では、参列者が親族中心であるため、派手さはないものの、心のこもった温かな見送りが特徴です。
出棺は式全体の締めくくりであり、故人を現世から送り出す最も象徴的な瞬間といえるでしょう。
火葬と収骨の流れ

告別式を終えたあとは、故人を火葬場へと移し、荼毘に付します。火葬は葬送の最終段階であり、遺族や親しい人が立ち会いながら静かに進められます。
火葬後には収骨と呼ばれる儀式があり、遺族が故人の遺骨を拾い上げて骨壺に納めることで一区切りを迎えます。ここでは火葬から収骨までの一般的な流れを整理してみましょう。
火葬の手順
出棺のあと、棺は霊柩車で火葬場へ運ばれます。到着後、まず遺族や参列者は炉前に集まり、僧侶の読経や合掌によって最後の別れを行うのが特徴です。
その後、棺は炉に納められ、火葬が始まります。所要時間はおおむね1時間から2時間ほどで、遺族は控室で待機するのが一般的です。
この時間は、遺族同士で思い出を語り合ったり、静かに心を落ち着けたりする大切な時間となります。火葬が完了すると職員から案内があり、収骨の準備へと移ります。
収骨の手順
火葬が終わると、遺骨を骨壺に納める「収骨」が行われます。日本では、二人一組で箸を使って遺骨を拾い上げ、骨壺へと移す習わしが広く行われています。
足の骨から順に頭の骨へと拾い納めるのが一般的で、これは「下から上へ」と遺骨を納めることで故人が立ち上がるようにという意味が込められています。遺族が協力して収骨する姿は、故人を家族の手で送る象徴的な場面です。
最後に喉仏の骨を納め、白い布で覆って骨壺に蓋をすると収骨は完了します。収骨を終えた骨壺は喪主や遺族が持ち帰り、後飾り祭壇や納骨まで大切に安置されます。
葬儀後の流れ

葬儀や火葬を終えても、遺族にはさまざまな務めが残されています。主なものは「精進落とし」「法要」「各種手続き」であり、これらを順序よく行うことで、葬送がひと区切りとなり、故人を正式に弔いながら日常生活へと戻っていくことができます。ここでは、それぞれの流れについて整理しましょう。
精進落とし
火葬後に行われる食事の席を「精進落とし」と呼びます。本来は喪に服していた遺族が精進料理を終えて通常の食事に戻る意味があり、近年では火葬後の会食を指す場合が一般的です。
料理を囲みながら、参列してくださった方々への感謝を伝えたり、故人の思い出を語り合ったりする場でもあります。家族葬の場合は親族だけの少人数で行われることが多く、形式にこだわらずアットホームな雰囲気で執り行われることも少なくありません。精進落としは単なる食事ではなく、故人を偲びつつ心を和らげる大切な時間です。
法要
葬儀後には、初七日、四十九日、一周忌といった節目ごとの法要を営むのが一般的です。特に四十九日は故人が来世へ旅立つ大切な日とされ、多くの遺族が法要と納骨を兼ねて行います。
これらの法要は菩提寺や自宅で僧侶を招いて行われ、遺族や親しい人が集まり、改めて故人を偲ぶ時間です。近年では、初七日を葬儀・告別式当日に「繰り上げ初七日」として済ませるケースも増えており、遺族の負担を軽減しつつも、故人を丁寧に弔う方法として広く行われています。
各種手続き
葬儀後には事務的な手続きも欠かせません。市区町村役場での埋火葬許可証の返却や、健康保険・年金・銀行口座などの名義変更や解約、相続に関わる手続きなど、多岐にわたります。
これらを放置すると後に不利益が生じるため、期限を意識して計画的に進めることが大切です。また香典返しも葬儀後に行う重要な準備のひとつで、通常は四十九日前後に贈るのが一般的です。
実務的な対応は精神的にも負担が大きいため、必要に応じて専門家や葬儀社に相談するのも安心につながります。
初めてでも安心できる家族葬専門式場「はないろ」がおすすめ

家族葬を考えるとき、多くの方が心配されるのは「費用はどのくらいかかるのか」「どんな準備が必要なのか」という点です。慣れない中で進める葬儀は不安が伴いますが、専門式場を選ぶことで安心感が大きく変わります。
「はないろ」は家族葬に特化した式場として、明朗な費用体系と複数のプランを用意し、火葬式から家族葬プラスまで幅広く対応しています。24時間365日体制で経験豊富なスタッフが支え、葬儀当日だけでなく、法要や仏壇・位牌、手元供養など葬儀後の相談まで一貫してサポート。背伸びをせずに、しかしきちんとしたお別れをしたいと願うご家族にとって、心強い選択肢となるでしょう。
まとめ
家族葬は、規模を抑えて身近な人だけで故人を送るため、落ち着いた雰囲気で心を込めた時間を過ごせるのが大きな魅力です。
準備から通夜、告別式、火葬・収骨、葬儀後の手続きまで一連の流れを理解しておくことで、不安を減らし安心して式に臨めます。とはいえ、初めて葬儀を経験する方にとっては分からないことも多く、費用や段取りに戸惑う場面も少なくありません。
そんなときに心強い存在となるのが、家族葬専門式場「はないろ」です。明朗なプランと経験豊富なスタッフによるサポートで、ご遺族の想いを大切にしながら、無理のないお別れを形にできます。
もし家族葬を検討されているなら、まずは「はないろ」へご相談ください。24時間365日対応の無料相談や資料請求を利用すれば、安心して最初の一歩を踏み出せるでしょう。