お葬式が終わったら
お葬式が終わったら
遺族年金について
一家の家計を担っていた大黒柱が亡くなると、残された家族は悲しみと共に生活を維持する困難さに直面します。そこで、日本では国民年金法と厚生年金保険法によって遺族に公的な年金を支給する仕組みがあります。ここでは、遺族年金の種類や受給資格、支給額等についてご紹介いたします。
遺族年金とは
被保険者が死亡した際に、残された家族へ支給される年金のことを「遺族年金」と言います。
一家の家計を担っていた世帯主の死亡は、残された家族に深刻な経済不安をもたらします。子供が小さかったり、配偶者が仕事に就いていない場合はなおさらです。
そこで日本では、国民年金法と厚生年金保険法によって、「遺族年金」を支給する仕組みがあります。残された家族を保護する目的で定められた公的な制度です。
大きく分けて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、給付内容は被保険者の働き方や子供の有無によって以下のような違いがあります。
| 18歳未満の子供 | 給付内容 | |
| 自営業の場合 | あり | 遺族基礎年金 |
| なし | 寡婦年金あるいは死亡一時金 | |
| 会社員の場合 | あり | 遺族基礎年金+遺族厚生年金 |
| なし | 遺族厚生年金 |
遺族が遺族年金を受け取れる最低条件は、被保険者が、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が、国民年金加入期間の3分の2以上あることをクリアしている必要があります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は自営業者などの国民年金加入者を対象としています。
未成年の子供の生活を保護する意味合いが強く、18歳未満の子供(障害年金の対象者である場合は20歳未満)がいる場合に支払われます。
18歳未満の子のいる配偶者、また配偶者が無く子のみの場合は子に支給されます。
遺族基礎年金は、遺族が妻、夫に関係なく、「配偶者」として同条件で扱われます。
但し、配偶者のみの場合、また子供が18歳以上の場合は支給されませんので、注意が必要です。
受給の条件や受給方法については「遺族基礎年金の受け取り方」で詳しくご紹介しています。
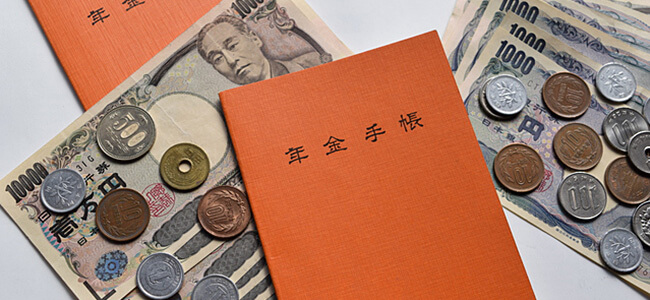
遺族厚生年金
遺族厚生年金は会社員など厚生年金の加入者を対象とした遺族年金です。
被保険者が死亡した場合、被保険者の配偶者、または子、55歳以上の夫または父母、18歳未満の孫、55歳以上の祖父母が、この並びの優先順位で最も高い人が給付対象となります。
支給対象は遺族基礎年金よりも広いものの、「配偶者」が妻か夫かによって支給条件が変わるため注意が必要です。
給付対象が妻であった場合は妻が死亡するまで支給されますが、夫の死亡時に妻が30歳未満であった場合は、夫の死亡後5年、子供がいる場合は子が18歳になるまでと決められています。また、夫、父母、祖父母に給付される場合は、55~65歳の期間に限られます。
詳しくは「遺族厚生年金の受け取り方」でご紹介してますので、参考にしてみて下さい。

寡婦年金
被保険者が自営業で子が18歳以上の場合、残された遺族に支給される年金はありません。この場合、残された遺族は経済的に不安定な状態になります。
こういった対象を救済するのが「寡婦年金」です。
寡婦年金を受給できるのは妻のみであり、妻が主に家計を支えていたとしても残されたのが夫である場合は支給されません。「男が家計を維持する」という時代の名残かもしれません。
寡婦年金を受給するには一定の条件があり、以下を満たす必要があります。
・夫が10年以上年金を納めている(平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要)
・夫と十年以上婚姻関係にある
・夫に生計を維持されていた
・夫が老齢年金や障害年金を受給していなかった
上記を満たす60歳以上65歳未満の妻を対象に支払われます。
寡婦年金の額は一律ではなく、亡くなった夫が本来もらうはずだった老齢年金の3/4(75%)となります。
もし子供が18歳になるまでの間遺族基礎年金を受給していても、妻が60歳になればそこから5年間寡婦年金を受給することが可能です。
遺族年金をもらえないケース
遺族年金についてご紹介しましたが、遺族年金は一定の条件を満たしていても受給できない可能性があります。
次回は「遺族年金がもらえないケース」についてご紹介します。