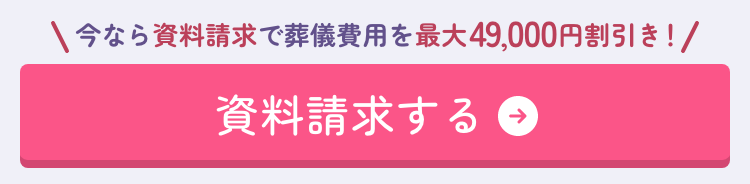お葬式のマナー
お葬式のマナー
忌引とは?お葬式で会社を休む方法
会社員の場合、親族のお葬式に出席する場合は「忌引き」扱いになります。突然このような休暇を取得しなければならなくなった時、一体どのようにすればよいのか慌ててしまうこともあるでしょう。もしもの時の為に、ここで忌引きの定義や一般的な日数、報告の仕方などについて把握しておきましょう。
忌引きとは
「忌引き(きびき)」とは、家族や近しい親族が亡くなった際に、お通夜やお葬式の準備や参列、喪に服すなど一定期間学校や職場を休むことが認められる制度です。日本では古くから、身内に不幸があった場合に一定期間社会活動を控える風習があり、その慣習が現代でも「忌引休暇」として受け継がれています。配偶者や父母、子ども、兄弟姉妹、祖父母などが対象とされ、関係の近さによって休暇の日数が変わるのが一般的です。企業や団体では、就業規則で取得条件や日数が細かく決められている場合が多く、有給休暇とは別に認められていることがほとんどです。
忌引きと有給休暇の違い
忌引き休暇と有給休暇はどちらも休暇の制度ですが、趣旨や取得の仕方に明確な違いがあります。忌引き休暇は、家族や親族の不幸というやむを得ない事情に対応するために企業が設けている「特別休暇」としての側面があり、一般的に有給とは別枠で扱われます。一方、有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法で定められた休暇で、理由を問わず取得可能であることが特徴です。忌引きは就業規則に従って取得するため、対象となる親族の範囲や必要書類が定められていることもあります。もし企業側に忌引き休暇制度が用意されていない場合は、有給休暇で対応する必要がありますので、事前に制度の有無を確認しておくと安心です。
忌引き休暇の一般的な日数
忌引き休暇で休める日数は、誰が亡くなったか(親等)によって変わります。一般的な基準としては、両親・配偶者・子どもなどの一親等の場合は5〜10日、祖父母・兄弟姉妹といった二親等の場合は3〜5日程度が目安とされています。三親等以降(叔父・叔母・いとこ等)になると1〜2日程度、もしくは忌引き扱いが認められない場合もあります。ただし、この日数はあくまで「目安」であり、総務や上司に確認をとりましょう。
| 亡くなった人 | 日数 | |
| 一親等 | 両親・配偶者・子ども | 5~10日 |
| 二親等 | 祖父母・兄弟姉妹 | 3~5日 |
| 三親等以降 | 叔父・叔母・いとこ等 | 1~2日、もしくは忌引き扱い無し |
忌引きの日数の数え方
忌引きの日数を数える場合は、親族が亡くなった日あるいはその次の日を1日目としてカウントします。忌引きは通常土日祝日も含めて数えますが、親族が遠方にいて移動に1日以上かかる場合は、移動にかかる日数分を追加で取得できることもあるようです。
忌引きの日数の数え方は会社の規定によっても異なりますので、詳しくは総務担当に確認してみましょう。
忌引きはどのように伝える?
●直接上司に自分で伝え、後ほどメールを
忌引き休暇を取得する場合は、まず直属の上司に相談しましょう。仕事が忙しい場合など、なかなか伝えづらい状況のこともあるかも知れませんが、直接伝えるのがマナーです。親族の死は悲しい出来事であるとともに、お葬式は大切な儀式です。会社側も理解を示してくれることがほとんどですが、仕事の調整などで同僚や上司の協力を仰ぐ必要もあるため、引継ぎなどはしっかり行うようにしましょう。
また、忌引き休暇をもらう旨を直接伝えた後は、不在時の連絡先や、お葬式が行われる住所などをメールで送りましょう。メールで送れば住所の聞き間違えもなく、後ほど見直すこともできます。会社によっては弔電を送ってくれる場合もありますので、メール連絡も早めにするのがベターです。
上司が出張などで不在の場合や、自身が出社できないような状況の場合は、チャットなどのツールを使用してまずは第一報を入れると良いでしょう。最近は社内のコミュニケーションツールとしてSNSを使用する会社も多く、急ぎの連絡にはとても便利です。
その後、詳細を電話やメールで伝えるとともに、会社の規定に従って人事や総務部に忌引き休暇の旨を伝えます。
●取引先には上司から伝えてもらう
忌引き休暇でクライアントとの打ち合わせや約束事ができなくなってしまう場合、欠席の旨は上司や同僚から伝えてもらうようにしましょう。本人が直接連絡すると、取引先に弔電や香典をくださいと言っているのと同じと捉えられる可能性があるからです。

忌引き伝え方の例
親族の死はやむを得ない自体ではありますが、急にお休みをもらう旨を丁寧に伝える必要があります。以下に、場面別の伝え方をご紹介しますので、参考にしてください。口頭でもメールでも、忌み言葉を使わないように気をつけましょう。
●上司へ忌引きの伝え方
————————————————————————————————
大変急な話なのですが、先日〇月〇日に父が亡くなりました。〇日から7日間の間、忌引きをいただけますでしょうか。葬儀日時については、決まり次第メールでご連絡いたします。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
————————————————————————————————
●上司や総務へメールでの伝え方
————————————————————————————————
忌引き取得の願い
お疲れ様です。〇〇です。
表題の件、父の不幸のため、以下のとおり忌引きを取得したくご連絡いたします。
忌引き:〇月〇日~〇月〇日 〇日間
故人:〇〇 〇〇 (読み仮名もあると丁寧) 享年〇〇
続柄:父
葬儀日時:通夜 〇〇年〇月〇日
告別式 〇〇年〇月〇日
納骨 〇〇年〇月〇日
葬儀会場:~~~~~会場
(住所)~~~~~~~~~~~
(電話)~~~~~~
※まだ葬儀日時が決まっていない場合は「決まり次第ご連絡いたします。」と記載
休暇中連絡先:(携帯)~~~~~~
(メールアドレス)~~~~~~~~~~~
以上
ご迷惑をおかけし申し訳ありませんが、ご承認のほどよろしくお願いいたします。
〇〇
————————————————————————————————
もしものことがあった際にはだれでも冷静でいられないものですが、会社への対応は上記を参考にしてみて下さい。
忌引に書類は必要?
忌引きによる欠席が正式に認められるためには、「会葬礼状」や「火葬許可証」、「死亡通知書」のコピーなどの証明書類の提出を求められることがあります。
必要な書類は事前に総務に確認しておくと良いでしょう。証明書類を提出するタイミングは、基本的に忌引き明けの出社時で構いませんが、事情によっては事前提出を求められることもあります。いずれの場合も、「書類をいつ、どうやって提出するのか」を確認し、遅延がないように準備しておくと良いでしょう。万が一、書類が用意できない場合は、事前にその旨を相談すると柔軟に対応してもらえることがあります。