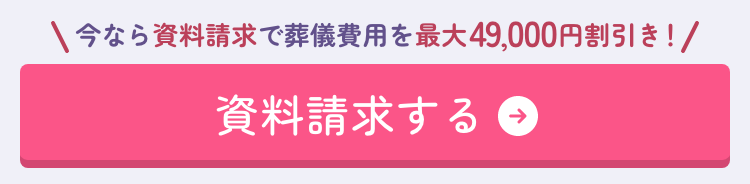お葬式の準備
お葬式の準備
令和のお葬式の平均費用は?大きく変わるお葬式のスタイル
お葬式をどのように執り行うかは、人生の最期をどう迎えたいかを考える機会にもなります。近年、日本ではお葬式のスタイルが多様化し、お葬式費用の相場も変遷してきました。「昔は高額だったお葬式が、令和の時代にはずいぶん手頃になった」と感じる方もいるかもしれません。その背景には、お葬式の規模縮小と、家族葬・直葬(火葬式)といった選択肢の拡がりがあります。本記事では、令和のお葬式スタイルをまず紹介しつつ、過去10年で変わった平均費用や、家族葬が選ばれる理由、そして「自分はお葬式に何を求めるか」によって選ぶべきスタイルを考えていきます。
令和のお葬式のスタイルとは
令和期の日本で見られるお葬式スタイルは、従来の「一般葬」に加えて、より小規模・簡素な形式の「家族葬」「一日葬」「直葬(火葬式)」などが選ばれることが増えています。これらの選択肢が存在感を増してきたのが、近年の傾向の一つです。まず「一般葬」とは、通夜・お葬式・告別式といった儀式をきちんと行い、故人と関係のあった親戚・友人・近隣・仕事関係など広く参列を呼ぶ形式です。会葬者を迎えるための場所、祭壇、飲食・返礼品などの費用がかかるのが特徴です。
一方、「家族葬」は、通夜・お葬式・告別式といった流れは残しつつ、参列者をごく近しい関係者に限定する形式です。地域性や故人との関わりにもよりますが、たとえば親族・親しい友人に限る、あるいは少人数で丁寧に見送るという志向が強くなっています。「一日葬」は、通夜を省略し、お葬式・告別式を1日に凝縮して行う選択肢です。時間や準備の手間を抑えたいという要望に応じて採られることが多くなっています。
そして「直葬(火葬式)」は、通夜・お葬式・告別式といった儀式を省き、火葬のみを行う最も簡素な形式です。宗教儀式や参列者向けの振る舞いを省略する分、費用・時間の両面で抑えられる選択肢として近年注目されています。こうした多様な形が並行して存在しているのが、令和時代のお葬式スタイルだといえます。選ぶ形式によって必要な費用・準備・参列者対応などが大きく変わるため、まずどのスタイルを望むかを明確にすることが出発点になります。
10年前から大きく下がったお葬式の平均価格
令和期に入ってからのお葬式費用の変化を見ると、過去10年で平均額は明確な低下傾向を示してきました。これはお葬式の「規模縮小化」やスタイルの見直しと密接に結びついています。
お葬式に関する定点調査を行う鎌倉新書の「お葬式に関する全国調査」によれば、2013年時点ではお葬式にかかる平均費用は約202.9万円という数字が示されています。そこから徐々に下がり、2022年には110.7万円まで低下しました。その後、2024年の調査では118.5万円とやや上昇傾向も見られますが、全体としては過去の水準よりも大幅に抑えられている水準です。
この変化は、お葬式そのものにかかる費用(会場使用、祭壇、お葬式スタッフ、霊柩車・運搬費など)だけでなく、飲食代や返礼品(香典返しなど)といった参列者数依存の費用が構成要素として含まれる点が鍵です。参列者数が減少すれば、飲食・返礼品にかかる変動費が下がります。2024年調査では、お葬式そのものにかかる平均額が約75.7万円、飲食や返礼品部分が約42.7万円という値が報じられています。これらの比率を見ると、「お葬式本体」費用と「参列者対応」費用の双方が削られやすいという構図が浮かび上がります。
さらに、参列者人数の変化も影響しています。2013年当時の平均参列者数は78人前後でしたが、徐々に減少し、2020年には55人、2022年には38人まで落ち込んでいます。このようなお葬式規模の縮小が、お葬式コストそのものを下げる原動力となっています。
また、お葬式業界自体が「明瞭な価格表示」や「定額プラン」を導入する方向に動き始めたことも、費用低下の要因として指摘されています。以前はお葬式費用が不透明で、追加料金が後から発生することもありましたが、最近では見積もり提示や明細説明を前提とするお葬式社が増えています。
このように、過去10年ほどでお葬式の平均費用がかなり下がった背景には、規模を抑える方向の選択肢が広がったこと、参列者数の減少、業界側の価格透明化の動きなど、複数の要因が絡み合っています。
※参考:鎌倉新書「お葬式に関する全国調査」
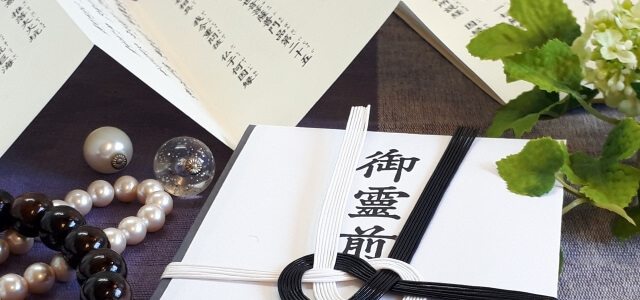
なぜ家族葬が増えたのか
家族葬が令和期に大きく増えてきたのは、お葬式に対する価値観の変化と社会構造の変動が関係しています。ここでは、代表的な要因を紹介します。
まず、経済的負担・費用抑制の観点があります。一般葬形式では会場使用料・祭壇・飲食・返礼品など、参列者対応にかかる費用が膨らみがちですが、家族葬では参列者数を抑えることにより変動費が大きく削減できます。これにより、式全体のコストを抑えつつ、質のある送別が可能となります。
次に、故人や家族の意向・プライベート重視の傾向です。大人数を招く式よりも、ゆったりとした流れで故人と向き合いたいという考え方が広まりつつあります。近年は、自己決定の重視や形式よりも「心を込めた送り方」が重視される傾向も見られます。さらに、地域・近隣・親族との結びつきの希薄化も影響しています。都市部・核家族化の進行とともに、地域社会や付き合いの輪が狭くなってきたため、広く人を招く必要性が薄れるという事情もあります新型コロナウイルス禍も、家族葬の普及を後押ししました。感染対策として、密になる大規模な式を回避し、小規模で進める傾向が強まりました。2022年の調査では、お葬式形式で最も多いのが家族葬(55.7%)という結果が出ています。
さらに、お葬式社側もこの流れに応じて、家族葬専門の式場展開やプラン展開を加速させています。既存のお葬式社や互助会が家族葬専用施設を設けるなど、供給側も体制を整えつつあります。
これらの要因が重なり合って、家族葬は令和期におけるお葬式スタイルの中心へと変化を遂げつつあります。ただし、2024年調査では家族葬は50.0%と、やや割合を下げ、一般葬が4.2ポイント増加したとの結果が出ており、アフターコロナの影響も読み取れます。つまり、家族葬が増えてきた背景には「コストを抑えたい」「身近な人で静かに送りたい」「付き合いの範囲が縮まった」など、多様な理由が複合していると言えるでしょう。