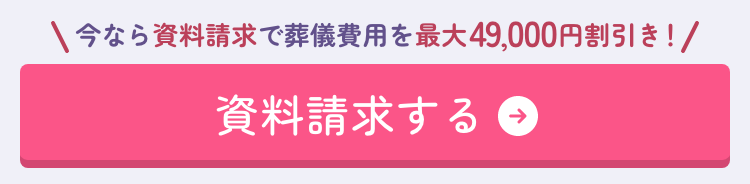お葬式の準備
お葬式の準備
生活保護受給者でも利用できる、「福祉葬」とは
お葬式の費用をどのように準備するかについてはいくつかの方法をご紹介してきましたが、いずれも「将来の為に少しずつ準備しておく」という性質のものでした。しかし、生活保護を受給している場合はどうなるでしょう?
今回は生活保護受給者のお葬式についてご紹介いたします。
生活保護受給は財産を保持しないことが前提
生活保護を受給するには、基本的に財産を保有していないことが前提となっています。財産がある場合はそれを処分して生活費にあてることが可能なためです。
以前、生活保護受給者が受給された金額を学資保険として貯蓄していたことが発覚し、没収されたというニュースが流れたことがありました。
様々な理由で生活に困窮している人に向け、税金を使って最低限の生活を保障するのが生活保護であるため、数百万単位の貯蓄を持つことは基本的に認められないのです。
生活保護受給者がお葬式を施行するためには
では生活保護受給者となった時点でお葬式を挙げることができないかというと、そんなことはありません。「葬祭扶助制度」という国の定める生活保護法があり、生活に困窮している人が一定の条件を満たせばお葬式の費用を受給できるというものです。この制度を利用し、葬儀社にお葬式の施行を依頼すれば費用の自己負担なくお葬式を施行することが可能です。
これを多くの葬儀社では「福祉葬」と呼んでいます。
葬祭扶助の制度については、「葬祭扶助制度とは?制度の内容と適用範囲」で詳しくご紹介していますので、参考にしてください。

福祉葬とはなにか
福祉葬とは、経済的な事情から通常のお葬式を行うことが難しい方に向けて、自治体が提供する「葬祭扶助」という制度を利用して行われるお葬式のことを指します。特に生活保護を受給している世帯や、それに準じてお葬式費用の負担が困難な家庭が対象となります。葬祭扶助によってお葬式にかかる費用の一部または全額が自治体から支給されるため、遺族は費用を負担せずにお葬式を行える点が大きな特徴です。
但し一般的なお葬式では通夜や告別式が行われ、参列者を招いて儀式を執り行うのが一般的ですが、福祉葬の場合はそうした儀式を省き、火葬のみを行う「直葬」の形が基本です。葬儀社による遺体搬送や安置、棺や骨壺の準備、火葬手続きなど、必要最低限の流れに絞られています。シンプルではありますが、遺族がきちんと最後のお別れをする時間を持つことは可能です。
福祉葬は「生活保護葬」や「民生葬」と呼ばれることもあり、名称が異なっても制度の内容は基本的に同じです。生活に困窮していても、尊厳を持って故人を送り出すことができる選択肢として、多くの自治体で利用されています。
福祉葬の流れ
福祉葬は、一般的な葬儀のように通夜や告別式を行わず、火葬を中心としたシンプルな形式です。まず、故人が亡くなると葬儀社によって遺体が搬送され、安置施設や自宅にて安置されます。その後、一定の時間が経過した段階で納棺を行い、棺へとご遺体をおさめます。納棺は家族が立ち会うことも可能で、最後に故人へ声をかけたり、お花を入れたりといった時間が持てます。
続いて出棺となり、棺は火葬場へ運ばれます。福祉葬では宗教儀式が含まれないため、読経や祭壇の準備は行われず、火葬炉の前で短いお別れの時間を取る形が一般的です。火葬後は遺骨が収骨され、遺族へ引き渡されます。その後の納骨や供養については葬祭扶助の範囲外となるため、各家庭の希望に応じて対応します。このように福祉葬は、搬送から火葬、収骨までの必要最小限の流れにより故人を見送るお葬式の形式です。
申請と手続き
福祉葬を行う際には、まず自治体の福祉課や福祉事務所に連絡することから始まります。死亡が確認された後、医師により死亡診断書が発行されますが、その後速やかに役所やケースワーカーに相談する必要があります。申請は必ず火葬前に行わなければならず、手続きが遅れると葬祭扶助が利用できない場合もあるため注意が必要です。
申請を行うと、自治体による審査が実施され、故人や申請者の経済状況が確認されます。資産がある場合や、親族に費用を負担できる人がいると判断されると、葬祭扶助が認められないケースもあります。このため、手続きの段階で必要な書類や条件をしっかり確認しておくようにしましょう。
申請に必要な書類や情報についても、「葬祭扶助制度とは?制度の内容と適用範囲」でご紹介していますが、自治体によって異なるケースがあるため、詳細は自治体に問い合わせることをお勧めします。
申請が承認されると、葬儀社と打ち合わせが行われます。葬儀社は遺体の搬送や安置を担当し、日程や火葬場の予約も手配します。福祉葬の流れは非常にシンプルで、
1. 死亡確認・申請
2. 遺体搬送と安置
3. 納棺
4. 火葬
5. 収骨
という順序が基本です。火葬後の納骨や供養にかかる費用は葬祭扶助の対象外となるため、遺族が別途対応する必要があります。このように福祉葬は、手続きからお葬式の進行までが明確に定められており、シンプルながらも必要最低限の流れが保証されています。

福祉葬を行う際の注意点
福祉葬を検討する際には、いくつか注意しておきたい点があります。まず、葬祭扶助はすべての人に自動的に適用されるものではなく、事前の申請と自治体による審査が必要です。資産や親族の有無、生活状況などが審査対象となるため、条件を満たさない場合は制度を利用できない可能性があります。
また、福祉葬は火葬のみが基本であり、通夜や告別式といった儀式は含まれていません。そのため、多くの参列者を招いたお葬式や、宗教的な儀式を希望する場合には別途費用が必要となります。費用が発生する追加サービスを希望すると葬祭扶助の範囲を超えるため、自治体の支給額を上回る部分は遺族が自己負担することになります。
さらに、福祉葬の対象範囲は自治体によって若干異なることがあります。例えば、棺や骨壺の種類、花束などの付帯サービスが含まれるかどうかは地域によって差があります。そのため、具体的な内容は事前に福祉課や葬儀社に確認しておくと安心です。
このように、生活保護受給者であっても自治体の支援制度を利用してお葬式を施行することが可能です。火葬を中心とした簡素な形ですが、最低限必要な流れが整っており、遺族が故人とお別れをする場を持つことができます。ただし、申請や審査といった手続きが必要が必要なうえ、自治体ごとに対応内容が異なる点