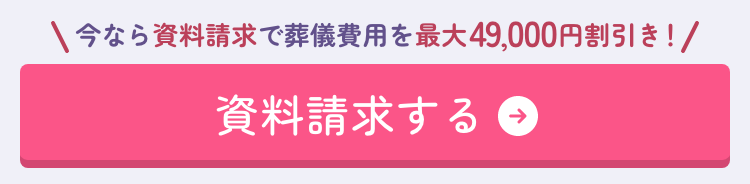お葬式の豆知識
お葬式の豆知識
家族葬と一般葬どちらが多い?それぞれの特徴を紹介
近年、日本のお葬式の形は大きく変化しています。かつては親族や友人、地域の人々が一堂に会する「一般葬」が主流でしたが、現在は親しい人たちだけで見送る「家族葬」が増えています。統計や調査によって差はあるものの、全体の約半数が家族葬を選んでいるといわれ、時代の流れを感じさせます。
ここでは、家族葬と一般葬の割合や特徴、増加の背景、そしてそれぞれのメリットとデメリットをご紹介します。
家族葬と一般葬の占める割合
近年のお葬式業界では、家族葬と一般葬が大きな2本柱となっています。
全国的な調査やお葬式会社のデータによると、現在のお葬式の約50%が家族葬、約40%が一般葬、残りの10%が一日葬や直葬などの形式といわれています。2000年代初めまでは一般葬が大多数を占めていましたが、この20年で家族葬の割合は大きく伸びました。特に都市部ではその傾向が顕著で、地域や親族間のつながりが薄まるにつれて、より小規模で私的なお葬式を希望する人が増えています。
新型コロナウイルスの流行期以降、感染拡大を防ぐ目的で参列者を限定するケースが増加したことも、家族葬普及の一因とされています。
その後も「少人数でも十分に心を込めたお葬式ができる」という考え方が定着し、新型コロナ終息後も家族葬が主流の一つとなりました。
一方で、地域によっては依然として一般葬を選ぶ方も多く、「昔ながらのお葬式で丁寧に弔いたい」という価値観も根強く残っています。お葬式の多様化が進むなかで、どちらの形式も一定の支持を集めているのが現状です。
家族葬と一般葬式はどう違う?
家族葬と一般葬の最大の違いは「参列者の範囲」と「規模」です。
家族葬はその名の通り、家族や親族、そして親しい友人のみで行う小規模なお葬式です。参列者は10〜30人程度で、通夜や告別式の流れは一般葬とほぼ同じですが、親密な雰囲気で故人との時間を大切にできます。訃報を広く知らせず、お葬式後に報告を行うケースも少なくありません。
一方、一般葬は親族に加え、仕事関係者や近隣住民など、幅広い人々が参列できる伝統的なお葬式形式です。規模は数十人から数百人にのぼる場合もあり、地域社会全体で故人を見送るという意味合いがあります。形式や儀礼も重視され、香典や返礼品、通夜振る舞いなどの準備が必要になります。
費用の面でも違いが見られます。調査によると、家族葬の全国平均は約110万円前後、一般葬は約190万円程度とされます。参列者数の差が費用に影響するため、家族葬のほうが比較的負担を抑えられます。ただし、香典収入も少なくなるため、必ずしも「安い」とは言い切れないのが実情です。
それぞれの特徴を理解したうえで、家族の意向や地域の慣習に合った形式を選ぶと良いでしょう。

なぜ家族葬が増えたのか
家族葬が増えた背景には、社会の変化が深く関係しています。まず第一に挙げられるのは、地域社会とのつながりの希薄化です。かつては近所づきあいが盛んで、地域ぐるみでお葬式を行うことが一般的でしたが、都市化の進行により、近隣との関係が薄れました。そのため、「多くの人を呼ぶ必要がない」と考える人が増えています。
また、コロナ禍による行動制限が、家族葬の定着を一気に後押ししました。大規模なお葬式が難しい中で、身内だけで行う形式が広まり、今では「無理をしないお葬式」として多くの人に受け入れられています。
さらに、宗教儀礼へのこだわりが薄れたことも理由の一つです。現代では宗教にとらわれず、自由な形式で故人を見送りたいという考え方が増えています。音楽葬や自宅葬など、個人の想いを反映するスタイルが選ばれるようになったのもこの流れの中にあります。
加えて、経済的な要因も無視できません。お葬式費用を抑えたいというニーズや、香典返し・会食準備などの手間を減らしたいという理由から、コンパクトな家族葬を選ぶ人が増えています。少子高齢化が進むなかで、身内だけで静かに見送るという考え方は今後も主流になっていくと考えられます。
家族葬のメリットとデメリット
家族葬には多くのメリットがあります。
まず、少人数のため準備や進行が比較的スムーズで、遺族の負担を軽減できる点です。参列者が家族や親しい友人のみのため、形式にとらわれず、故人らしい雰囲気でお葬式を行うことができます。
また、ゆっくりと故人と向き合える時間が確保できるのも大きな魅力です。弔問客への対応に追われることがなく、落ち着いて最後の時間を過ごせます。費用の面でも、会場規模や接待費を抑えやすいのが特徴です。
一方で、デメリットも存在します。
まず、参列を希望していた人がお葬式に参加できず、後日弔問が増えるケースがあります。また、家族葬に理解のない親族や知人から「知らせてほしかった」と不満を持たれることもあるため、事前に説明をしておく配慮が必要です。
さらに、参列者が少ない分、香典の総額も減少します。そのため、費用を香典収入でまかなう予定だった場合、家計への負担が増えることもあります。
このように、家族葬は「静かに」「心を込めて」見送ることに適した形式ですが、周囲への伝え方やお葬式後の対応までを考慮して選ぶことが大切です。
最近では家族葬専用の斎場も増えており、経験も豊富です。家族葬のメリットやデメリット、起こりがちなトラブルについても熟知されていますので、見学会などに参加して相談してみると良いでしょう。