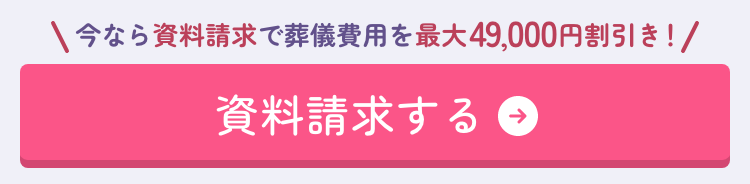お葬式の豆知識
お葬式の豆知識
枕団子とは?意味とその役割
仏事においてお供えされる「枕団子」は、故人の旅立ちを見守る大切な供物です。しかし、その意味や供え方、処分の仕方についてはあまり知られていません。ここでは、「枕団子とは何か」と、その由来や役割、正しいお供え方法、供えた後の取り扱いまでを丁寧にご紹介します。
枕団子とは
枕団子とは、仏事において亡くなった方の枕元にお供えするお団子のことを指します。人が亡くなると、その魂は極楽浄土への旅に出るとされており、その旅路の途中で空腹にならないよう、あらかじめ用意されるのが枕団子です。これは、故人が安らかに旅立てるようにという家族や周囲の人々の想いが込められた大切な風習の一つです。
このお団子は、葬儀の直前に供えられるものであり、一般的には白くて丸い団子を6個、あるいは7個、またはそれ以上の数を積み重ねてお供えします。団子の数や形は宗派や地域、家庭によって異なりますが、どの形であれ、故人への深い敬意と愛情を示す行為であることに変わりはありません。
お団子そのものは、上新粉や白玉粉で作られるシンプルなもので、香りや味付けが施されていないのが一般的です。あくまで供養のためのものなので、見た目も慎ましく、清らかさを象徴するように仕上げられています。日常的には目にすることのないこの枕団子ですが、身内に不幸があった際には重要な役割を担うため、事前にその意味や準備の仕方を知っておくことは大切です。

枕団子の由来と意味
枕団子の起源には、仏教にまつわる深い逸話が隠されています。お釈迦様が入滅された際に献上された香飯をとらなかったため、死後に団子を供えたことに由来していると言われています。こののちに故人に団子を供える習慣が生まれ、これが今日の枕団子へとつながったとされています。
団子を供える意味には、故人が無事にあの世へと旅立つことができるようにとの祈りが込められています。特に、「六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)」という仏教の教えにちなみ、故人が迷わず成仏できるように6個の団子を供えることが多いです。また、7個供える場合は、「六道を超えて極楽浄土にたどり着けるように」という願いが込められています。
枕団子には、単なる形式的な意味を超え、亡くなった方への感謝や尊敬の念、そして残された人々の「故人の成仏」に対する願いが込められています。団子は食べ物であると同時に、心を託す供物でもあるのです。枕団子には、作る人の心遣いが供養の一部として表れるとも言えるでしょう。
宗教や地域により若干の解釈の違いはありますが、枕団子をお供えする風習は、多くの日本人にとって「故人の魂を見送る第一歩」として、今も大切に守り継がれている文化です。
枕団子の供え方
枕団子は、故人が亡くなってから火葬されるまでの間、遺体の枕元にお供えします。多くの場合は、枕飾りと呼ばれる一式の祭壇に「枕膳(まくらぜん)」という供え物を並べる台を設け、その上に枕団子を置きます。枕団子は丸く成形され、数個を小皿や器に載せ、整然と積み上げるのが一般的です。
団子の数には明確な決まりはありませんが、6個・7個・13個・49個といった意味のある数が選ばれることが多く、それぞれに仏教的な意義が込められています。特に6個は「六道」を象徴し、故人がその全てを越えて成仏できるようにとの想いが表現されています。
団子をお供えする際には、置き方にも決まりがあります。6個の場合は、5個を円形に並べてその中央に1個を乗せるピラミッド型が基本です。このように積むことで「上へ上へと昇るように」という願いが込められているのです。
また、団子を載せる皿には半紙を敷くことがあります。この半紙は仏事用の折り方を用い、左が上になるように三角に折るのがマナーです。団子の向きや半紙の置き方にも一定の決まりがあるため、宗派や地域の風習に従って準備するようにしましょう。

枕団子の処分方法
枕団子は仏前に供えるものであるため、供養が終わった後の取り扱いにも注意が必要です。基本的には、お供えが終わった後、遺族が食べることで供養が完了するとされています。これは「お下がり」としての意味があり、故人と共に食を分かち合うという精神に通じています。
ただし、団子が傷んでいたり、衛生的に不安がある場合は、無理に食べる必要はありません。その際には、感謝の気持ちを込めて丁寧に処分するようにしましょう。例えば、白い紙に包んでから一般ごみに出す、あるいは庭先で土に埋めるなどの方法が取られることもあります。
また、団子をお供えした器や皿についても特別な扱いがされることがあります。地域によっては、この皿をあえて割って処分するという風習が残っているところもあり、これは「死を受け入れる」という象徴的な行為とも受け取れます。
宗派によっては、枕団子をお供えしない場合もあります。たとえば、浄土真宗では「すぐに成仏できる」という教義から、枕団子自体を供えないことが一般的です。こうした違いを尊重しつつ、地域の慣習や葬儀を執り行うお寺の指導に従って行動すると良いでしょう。
いずれにしても、枕団子は単なる儀式の一部ではなく、故人を偲び送り出すための大切な象徴です。その後の処分についても、感謝と敬意の気持ちを忘れずに行うことが、仏事における礼節と言えるでしょう。