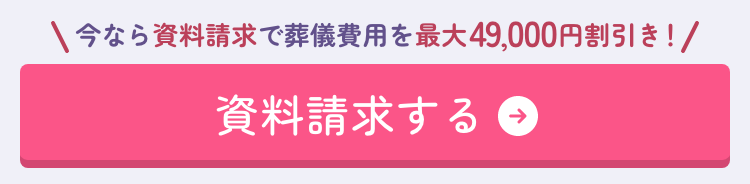お葬式の豆知識
お葬式の豆知識
記事公開日:
/
最終更新日:
湯灌の持つ意味とは?湯灌の流れと費用
人が旅立つ前に行う「湯灌(ゆかん)」は、故人の体を洗い清める大切な儀式です。生前の苦しみや汚れを流し、安らかに送り出す思いが込められています。ここでは湯灌の意味や由来、流れや費用などをご紹介します。
湯灌とは
湯灌(ゆかん)とは、亡くなられた方の体をお湯で洗い清める儀式のことをいいます。納棺の前に体を洗浄し、きれいに身支度を整えて旅立たせるという、日本に古くから伝わる習わしです。現世での汚れを落とし、来世への旅支度としての意味も込められています。1日の終わりに入浴する習慣がある日本人にとって、人生を締めくくる大切な行為とされており、納棺の儀式と同様に尊重されています。最近では専門の納棺師や葬儀社に依頼することが増えており、バスタブを移動させて自宅や会館で行うスタイルが一般的になりました。湯灌は遺族にとっても、故人にきれいな姿で旅立ってほしいという気持ちを表す大切な儀式となっています。
現在は、湯灌の代わりに故人の体をアルコールで清める「清拭(せいしき)」という儀式が取り入れられるようになり、湯灌を行わないことも増えています。昔は自宅で亡くなることがほとんどでしたが、現在は病院で亡くなることが増えているという時代の流れが背景にあるようです。
また、さまざまな事情で亡くなってから火葬するまでに時間が空いてしまう場合は、遺体の長期保存ができる「エンバーミング」という方法がとられることもあります。
湯灌の由来
湯灌の由来は仏教の影響を受けているとされ、古くは唐の時代に義浄(ぎじょう)という僧侶が訳した経典に記されていたものが日本に伝わったといわれています。人が亡くなるとき、現世での煩悩や苦しみを洗い流し、清らかな状態であの世へ旅立たせるという意味合いが込められていました。日本では入浴で一日の疲れを癒やす習慣がありますが、湯灌はその最終的な延長として「故人の一生のけじめをつける」行いとも考えられています。さらに、故人の体から流れ出る血や体液を洗い流し、衛生的に整えるという実務的な側面もあります。江戸時代などでは、家の規模や地域の習わしにより、自宅や寺院で行われていた記録も残っています。湯灌は単なる形式的な儀式ではなく、亡くなられた方への労いや祈りを込めた行為として大切に受け継がれてきたのです。

湯灌はどこで行う?
湯灌は、主に自宅や葬祭会館で行われます。かつては自宅で湯灌を行うことが一般的でしたが、最近では葬祭会館に湯灌用の設備が整っていることが多く、会館で行われるケースが増えています。専用のバスタブを備えた湯灌専用車で自宅に訪問し、浴槽を設置して行う移動型の湯灌もあります。どちらの場合も、専門の納棺師や湯灌スタッフが準備から終了までを担当するため、遺族は負担を減らして立ち会うことができます。湯灌に使用したお湯は、かつては自宅の床下や日陰に流す風習がありましたが、現在では業者が責任を持って持ち帰り、適切に処理することがほとんどです。設備や家の事情により場所を選べる点も、現代の湯灌の特徴といえるでしょう。故人の希望や遺族の意向に合わせて柔軟に選べるようになっているのが現在の湯灌です。
湯灌の流れ
●浴槽の準備、前準備
業者が故人と遺族に挨拶を交わした後、浴槽の搬入が行われます。浴槽の搬入後には、故人の爪や顔の表情を整え、硬直をときながら服を脱がせてバスタオルをかけます。爪切りは、洗体後に行われることもあります。
●口上(こうじょう)
これから湯灌という儀式が行われることが、口頭で説明されます。
●逆さ水・洗体
逆さ水は、故人の足元から胸元に向かって水をかけ、体を清める儀式で、遺族が行います。個の時、水をすくうひしゃくは左手で持つと決められています。湯灌で使われる水は常温であることが多いですが、遺族の意向により、お湯を足してぬるま湯にする場合もあります。逆さ水を作る際は、水にお湯を入れて温度調節を行います。また、逆さ水が行われる際は、肌が見えないようにタオルをかけたまま行われます。
逆さ水を行った後は、逆さの作法に従い、左足から右足に向かってシャワーを流します。これは業者の方が行うこともありますが、希望によっては遺族の方も一緒に洗うことも可能です。
●洗髪・顔そり・髭そり・洗拭き
洗体後には、シャンプーやリンスを使用して頭を洗い、ドライヤーで乾かして髪を整えます。その後、ぬれた布などで顔を拭き、顔そりを行います。顔を拭く際は、希望があれば遺族が行うこともできます。
●身支度
体のお清めが終わったら故人を床へ移して服を着させ、死に化粧を施します。着衣は、白い仏衣あるいは個人がお気に入りの服を着せます。どの服を着せるのかは宗教によっても異なりますが、日本人に最も多い浄土真宗では、故人が好きだった服を着せることが可能です。死に化粧は、希望により遺族が行うこともできます。また、ここでは、遺体から体液が流れ出ないよう、口や鼻、耳、肛門などに脱脂綿を詰めます。

湯灌に立ち合いは必要?
湯灌は、必ずしも遺族が立ち会わなければならないものではありません。基本的には喪主や近親者が立ち会うことが多いものの、状況により立ち合いなしで任せるケースも増えています。湯灌では、故人の肌が露わになる場面もあるため、立ち会いを控える方もいらっしゃいます。一方で、旅立ちの準備を共に行う大切な時間と考え、家族で見届けたいという遺族も少なくありません。実際には故人の尊厳を守るために、肌を見せないようタオルで覆いながら行われます。立ち合いは遺族の希望で選べますし、葬儀社側からも無理に参加を促されることはないため、気持ちに合わせて決めると良いでしょう。湯灌の立ち会いは、遺族にとっても故人との最後の触れ合いを深める貴重な時間として受け止められることもあります。
湯灌の費用
湯灌にかかる費用は、葬儀社や業者、地域によって差がありますが、おおむね5万円から10万円程度が相場です。基本的には湯灌のみの費用ですが、納棺や死化粧までセットで依頼する場合はさらにプラスになることもあります。近年は湯灌をオプションとして追加するスタイルが多く、葬儀プランに含まれていないケースも少なくありません。移動式の浴槽を利用するかどうか、または古式湯灌のようにお湯を使わない方法を選ぶかによっても金額は変わります。葬儀社によってはセット割引を用意していることもありますので、希望に応じて事前に見積もりを取ると安心です。費用だけでなく「どこで」「誰が」行うのかという条件にも注目して検討しておくと、納得のいく送り方を選べるでしょう。湯灌は一生に一度の大切な儀式ですから、しっかりと確認しておくのがおすすめです。
湯灌は、亡くなられた方への最後の贈り物ともいえる穏やかな儀式です。清め、癒し、感謝の気持ちを込めて行われる湯灌は、遺族にとっても大切な時間となるでしょう。故人にふさわしい旅立ちを支える意味で、湯灌という文化を知っておくことは役立ちます。