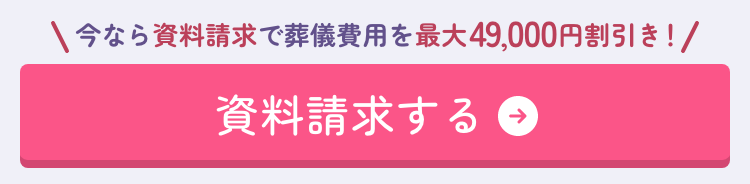お葬式の豆知識
お葬式の豆知識
ゼロ葬とは?遺骨を引き取らない選択
少子高齢化やお墓の継承問題を背景に、日本の葬送文化は大きく変化しつつあります。中でも最近注目を集めているのが「ゼロ葬」です。火葬後に遺骨を引き取らずに終える新しい弔いの形で、経済的負担を減らせる一方、文化的・精神的な課題も少なくありません。ここではゼロ葬の意味や特徴、メリット・デメリット、行い方を詳しく解説します。
ゼロ葬とは
近年、日本の葬儀や供養の在り方は多様化しており、家族葬や直葬、散骨、手元供養など従来の形式にとらわれないスタイルが広がっています。その中で注目されているのが「ゼロ葬」です。ゼロ葬とは、火葬後に遺族が遺骨を引き取らない葬送の方法を指します。一般的には火葬が終わると遺族が骨壺に遺骨を納め、墓地や納骨堂に安置したり、散骨や手元供養をしたりするものです。しかしゼロ葬では、そうした手順を行わず、火葬後にそのまま解散となります。
この考え方は宗教学者の島田裕巳氏が2014年に出版した著書『0葬 ― あっさり死ぬ』によって広く知られるようになりました。島田氏は「火葬したらそれで終わり。遺骨は引き取らずに火葬場に任せる方法」と説明しています。背景には、「墓を持たない選択をしたい」「遺骨の管理に負担をかけたくない」といった現代的な事情があります。欧米では火葬後の遺骨の引き取りは任意であり、残された遺骨を受け取らないことも珍しくありません。日本で「寂しい」と感じられるのは、文化的な死生観の違いからくるものといえるでしょう。
また、日本国内でも地域によって遺骨の扱い方が異なります。東日本では全ての遺骨を骨壺に納める「全骨収骨」が一般的ですが、西日本では三分の一程度を収骨する「部分収骨」が多く行われています。残骨灰は火葬場の供養塔や寺院に納められるため、遺骨をすべて持ち帰らないというスタイル自体はすでに存在しているともいえます。ゼロ葬は、こうした地域性や現代社会の価値観の変化を背景に登場した新しい葬送の形なのです。

ゼロ葬とゼロ円葬との違い
因みに「ゼロ葬」と似た言葉で「ゼロ円葬」がありますが、「ゼロ葬」と「ゼロ円葬」は別の意味になります。いずれも費用を抑えたお葬式の形態を指しますが、「ゼロ葬」は火葬後に遺骨を引き取らず、火葬場で処理してもらう葬儀の形式を指します。一方、「ゼロ円葬」は、生活保護受給者などが受けられる「葬祭扶助」を利用して、自己負担ゼロ円、つまり「費用をかけずに」お葬式を行うことをいいます。
ゼロ葬のメリットとデメリット
ゼロ葬は従来の葬儀や納骨のスタイルとは大きく異なり、その分メリットとデメリットが明確に存在します。
●ゼロ葬のメリット
まずメリットとして挙げられるのは、費用や手間が大幅に軽減されることです。通夜や告別式を行わないケースが多いため葬儀費用を抑えられ、またお墓の購入や維持費も不要になります。さらに、遺骨を引き取らないため、親族間でのお墓の管理を巡る負担や意見の食い違いを避けられる点も利点といえるでしょう。特に、身寄りが少ない人や、子どもに供養の負担をかけたくないと考える人にとって、合理的な選択肢となります。
●ゼロ葬のデメリット
一方でデメリットも少なくありません。第一に、ゼロ葬を受け入れてくれる火葬場や自治体は限られているため、希望しても実現が難しい場合があります。また、遺骨を残さないことに対して、親族や周囲の理解を得にくく、批判を受ける可能性もあります。宗教的な観点からも、僧侶を呼ばず供養の儀式を行わないことに抵抗を感じる人は少なくありません。
さらに、後になって「やはり遺骨を手元に残しておきたかった」と遺族が後悔することも考えられます。火葬後に残骨灰を個別に返還してもらうことは不可能なため、決断は取り消せません。経済的・実務的な利便性と、精神的・文化的な価値観との間でバランスを取ることが、ゼロ葬を選ぶ上での大きな課題といえるでしょう。

ゼロ葬の行い方
実際にゼロ葬を行うには、いくつかの手順と準備が必要です。まず重要なのは、希望する火葬場や自治体がゼロ葬を認めているかどうかの確認です。火葬場条例には「焼骨の引き取り」に関する規定があり、多くの自治体では火葬後すぐに遺骨を引き取るよう求められています。しかし一部では、一定期間を経過した後に自治体が処分を行うと定めているところもあり、そうした地域であればゼロ葬が可能となります。
葬儀社を通じて「遺骨を引き取らない」旨を事前に申し出ることが一般的ですが、対応は地域や火葬場によって異なります。西日本のように部分収骨が主流の地域では、火葬場に遺骨を残すことが比較的スムーズに行えますが、東日本では全骨収骨が慣例であるため「前例がない」と断られることもあります。その場合、葬儀社が一度遺骨を預かり、後日散骨などを代行する形で「実質的なゼロ葬」を行うケースもあります。
また、遺族の合意形成も欠かせません。ゼロ葬は火葬の当日にはっきりと意思を示さなければならず、時間的猶予がありません。もし家族間で意見が分かれていれば、実行は困難になります。そのため、本人がゼロ葬を望む場合には、生前にエンディングノートや遺言で明確に意思を残しておくことが望ましいでしょう。
さらに、ゼロ葬後の遺骨は火葬場や自治体によって供養塔に納められたり、専門業者によって処理された後に寺院や霊園に埋葬されたりします。都市伝説的に「産業廃棄物として処理される」といった説もありますが、現在では遺族感情や環境への配慮から、適切に供養されるケースが一般的です。事前に火葬場や自治体に確認し、最終的な行方を把握しておくことも大切といえるでしょう。
ゼロ葬で後悔しないために
ゼロ葬を選択することは、経済的な負担を減らし、後継者のいない人やお墓を維持できない人にとって合理的な方法となります。しかし、その一方で「本当に遺骨を残さなくてよかったのか」と後悔する遺族が出る可能性は否めません。そのため、後悔を避けるためにはいくつかの準備が欠かせません。
まず大切なのは、本人の意思を明確にし、家族と共有しておくことです。ゼロ葬を希望する理由や考え方を事前に家族に伝え、理解を得ておくことで、葬儀当日に迷いや衝突が生じるのを防げます。また、親族や周囲からの批判に対しても「故人の希望である」と説明できるため、遺族の精神的負担を軽減することにもつながります。
次に、実際にゼロ葬が可能かどうかを事前に確認しておく必要があります。火葬場や自治体の方針によっては認められない場合があるため、希望する地域の情報を調べておくことが重要です。もしゼロ葬が難しい場合には、小さな骨壺にごく一部だけを収骨し、残りを火葬場に委ねる「簡易的なゼロ葬」に近い方法を検討することもできます。
さらに、心の整理も欠かせません。遺骨が手元にないことで、後になって故人を偲ぶ場所がないと感じる人もいます。その場合、形のある供養にこだわらず、写真や思い出の品を身近に置いたり、法要やお別れの会を開いたりするなど、別の方法で気持ちを整理することができます。
ゼロ葬は現代社会の課題である少子高齢化やお墓問題に応える新しい選択肢であり、決して「愛情がないから選ぶもの」ではありません。本人と家族が納得したうえで準備を整えておけば、後悔のない形で実現できる可能性は十分にあります。大切なのは「自分たちにとって最も自然で無理のない弔い方」を選ぶことだといえるでしょう。